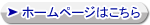今泉松原植生・291年前の決断(文化部による調査)
下の地図は約291年前の陸前高田市付近の海岸線や川岸を2010年度の地図に当てはめたものです。参照は今泉同人誌・みちしるべ等によります。8月24日付けでブログ紹介した地図に比べて88年が経過して立神浜は新しい河口付近に伸びてきて,対岸には田の浜と呼ばれる砂浜までが形成された模様です。
伊達騒動の後に伊達吉村公による財政立て直しのため,領地を再検地したとのことです。地名も新たに設定され,高田村方面では本宿・中宿・下宿・曲松・中田・沼田等の名があるのに対して,今泉村方面では土手影・木場・砂盛・中堰等の地名が加えられた模様です。
慶長三陸津波の被災地では金山所有は名ばかりに,直轄地による様々な諸事情から仙台藩の命を受けて,今泉村や高田村でも幾多の先人によって,田畑の再興及び開墾に挑んできたと聞きます。しかし,ただでさえ天災が多かったと言われる江戸時代のこと,海からの強風によって絶えず砂塵をかぶったり,海水が浸入したりして草木の育たない不毛の土地だったことでしょう。その後背地の田や畑も砂をかぶったり,潮風を浴びたり,海水が浸入したりして農作物の収穫できないことが度々あったとの事。
歴史に名を残さないまでも,数多くの先人による幾多の汗と涙があった筈です。担当者の先祖も塩田開発のために藩から命を受け何処より学区の南部の長部へ移住し,山林や海岸についてある程度の権限を戴きながら,塩釜による製塩方法等の試行錯誤を繰り返したと聞きます。
潮風や砂塵などから平野の耕地を守るため,私財を投じて長年にわたり不毛の砂地に苦労を重ねて松苗を植え,立派な松林に育てることに成功した先人について,多くの資料ではその名が語られます。松植生の結果,開墾された田畑。村は益々発展して行くという物語。藩の命はあっても藩体制というより各村独自の取り組み。互いの競争。ここ高田の平野にても菅野杢之助等によって,いち早く高田村側では松植林に成功して田畑の開墾が進められた模様です。
一方,今泉側では洪水が繰り返され依然として塩分の多い湿地だったので,奈々切の開拓は遅れてしまう,そんな状況で291年前の享保10(1725)年から松坂新右衛門定宣によって自費を投じて海岸線約720m,面積9.3haにアカマツを植栽したとあります。義父である松坂十兵衛定好は父親の代より御金山下代・大肝入・鍛冶奉行・御鉄方役などを兼務し,伊達領内の鉱山奉行,気仙郡の大肝入を勤め地方行政を担当したようです。今泉村の通称御蔵(垂井ヶ沢)に穀倉蔵を建設する等,気仙郡全体のための業績を上げた御仁との事でした。その入り婿の新右衛門は今泉の未来のために立ち上がり,今泉松原植林を遂に成功させ,後世の田畑開墾に道しるべをつけさせた御仁ということです。因みに,その後何度も造林され,そのうちの1本は天保10(1839)年に芽吹き,東日本大震災でも津波に耐えて,立ったままの状態で残った松,『奇跡の一本松』として有名になりました。昭和30年,陸前高田市の市制施行により,高田松原と今泉松原を合わせて高田松原と呼ぶようになったとあります。

伊達騒動の後に伊達吉村公による財政立て直しのため,領地を再検地したとのことです。地名も新たに設定され,高田村方面では本宿・中宿・下宿・曲松・中田・沼田等の名があるのに対して,今泉村方面では土手影・木場・砂盛・中堰等の地名が加えられた模様です。
慶長三陸津波の被災地では金山所有は名ばかりに,直轄地による様々な諸事情から仙台藩の命を受けて,今泉村や高田村でも幾多の先人によって,田畑の再興及び開墾に挑んできたと聞きます。しかし,ただでさえ天災が多かったと言われる江戸時代のこと,海からの強風によって絶えず砂塵をかぶったり,海水が浸入したりして草木の育たない不毛の土地だったことでしょう。その後背地の田や畑も砂をかぶったり,潮風を浴びたり,海水が浸入したりして農作物の収穫できないことが度々あったとの事。
歴史に名を残さないまでも,数多くの先人による幾多の汗と涙があった筈です。担当者の先祖も塩田開発のために藩から命を受け何処より学区の南部の長部へ移住し,山林や海岸についてある程度の権限を戴きながら,塩釜による製塩方法等の試行錯誤を繰り返したと聞きます。
潮風や砂塵などから平野の耕地を守るため,私財を投じて長年にわたり不毛の砂地に苦労を重ねて松苗を植え,立派な松林に育てることに成功した先人について,多くの資料ではその名が語られます。松植生の結果,開墾された田畑。村は益々発展して行くという物語。藩の命はあっても藩体制というより各村独自の取り組み。互いの競争。ここ高田の平野にても菅野杢之助等によって,いち早く高田村側では松植林に成功して田畑の開墾が進められた模様です。
一方,今泉側では洪水が繰り返され依然として塩分の多い湿地だったので,奈々切の開拓は遅れてしまう,そんな状況で291年前の享保10(1725)年から松坂新右衛門定宣によって自費を投じて海岸線約720m,面積9.3haにアカマツを植栽したとあります。義父である松坂十兵衛定好は父親の代より御金山下代・大肝入・鍛冶奉行・御鉄方役などを兼務し,伊達領内の鉱山奉行,気仙郡の大肝入を勤め地方行政を担当したようです。今泉村の通称御蔵(垂井ヶ沢)に穀倉蔵を建設する等,気仙郡全体のための業績を上げた御仁との事でした。その入り婿の新右衛門は今泉の未来のために立ち上がり,今泉松原植林を遂に成功させ,後世の田畑開墾に道しるべをつけさせた御仁ということです。因みに,その後何度も造林され,そのうちの1本は天保10(1839)年に芽吹き,東日本大震災でも津波に耐えて,立ったままの状態で残った松,『奇跡の一本松』として有名になりました。昭和30年,陸前高田市の市制施行により,高田松原と今泉松原を合わせて高田松原と呼ぶようになったとあります。

2016/08/29 14:10 |
2016年08月