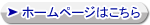慈悲に富み育英に務む名僧・上野英俊方丈様
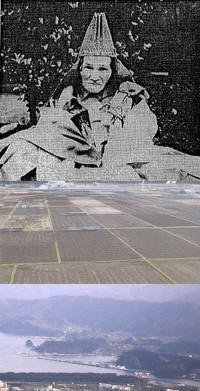 右の写真は名僧として郷土に偉大な足跡を残した上野英俊方丈様(1847~1913.2)です。文化部による調査です。今泉の先人物語等を参照しました。仙台人名大辞書にも紹介されてあるとの事ですが,生まれは仙台の人で真言宗本寺から派遣されて歴代35世,貞観11(869)年の震災より2年後に上野(和野→高田)村の金剛寺洞に創建された歴史があり,正保2(1645)年に今泉村に移っていた金剛寺の住僧となったそうです。当時,真言宗の道場(学問所)になっており,気仙郡内の13ヶ寺と気仙沼大島の2ヶ寺,合わせて15ヶ寺からそれぞれ弟子が修業に来て,英俊方丈様の薫陶(人柄や人格人徳人品で人を感化させ良い方向に導く事)を受けることができたとあります。
右の写真は名僧として郷土に偉大な足跡を残した上野英俊方丈様(1847~1913.2)です。文化部による調査です。今泉の先人物語等を参照しました。仙台人名大辞書にも紹介されてあるとの事ですが,生まれは仙台の人で真言宗本寺から派遣されて歴代35世,貞観11(869)年の震災より2年後に上野(和野→高田)村の金剛寺洞に創建された歴史があり,正保2(1645)年に今泉村に移っていた金剛寺の住僧となったそうです。当時,真言宗の道場(学問所)になっており,気仙郡内の13ヶ寺と気仙沼大島の2ヶ寺,合わせて15ヶ寺からそれぞれ弟子が修業に来て,英俊方丈様の薫陶(人柄や人格人徳人品で人を感化させ良い方向に導く事)を受けることができたとあります。時は明治維新後の学制・税制等の改革,殖産興業等,近代的封建国家から西欧型国家に変貌させることで欧米列強進出に対抗するという時代背景によって様々な要請が当地にも押し寄せつつあった時期でしょう。
方丈様の生前の功績として明治28(1895)年に発案された遠救社(クラッコ)の組織があるとの事です。既に明治14(1881)年に興された如意講を発展させたものとか。往時は,天候に左右され不作の連続でした。他国よりは穀類の一切が入手不能となるため,寺地の一部に備荒倉を建て,連救社と名付け,穀類を備蓄し,不作の時には,分け合って急場を凌いだとあります。寒冷気候に対処できるような品種改良等の農業改革は後世の話です。その組織は頼母子講(無尽講)の一つと考えられます。小さなグループが地域でつながり,お金を積み立て「融通」する関係を指しています。お互い顔が分かり,信頼できて,借りたものをしっかり返せる,「たすけあい」の関係なのだそうです。
明治8(1875)年に今泉村と長部村が合併して気仙村となったとは言え,川沿いの宿場と海沿いの漁村では互いのことを別物と考えるのが双方の考え,とか根強く巷に蔓延る時期だったそうです。にも関わらず,明治29(1896)年三陸津波で被災した際には,ご本人からのお声掛けで,今泉,長部の分け隔て無く,長部湊の復旧のために気仙沼方面まで続く道路整備を震災復興事業として,田の浜産業道路整備をも加えて発案したそうです。
明治37(1905)年から翌年にかけて,世は日露戦争で国家総動員状態の最中,既に高田道路が開通して大船渡や世田米には繋がっており,ご当人はかつての村境における柵(しがらみ)に拘らぬ度量の方とか。その延長として,今泉(気仙)松原裏の田(奈々切・木場・中堰地区等,高田道と言われた地)の区画整理を指導した農地改良の先駆者でもあったそうです。つまり,当時300年前からの慶長三陸震災復興を艱難辛苦の挙げ句,遂に実現させた発案者と言うことになります。
御自らは身体の不遇に耐えつつ仏の慈悲を渗透させ,自寺の檀徒であるなしにかかわらず,向学の徒に奨学金を援助したり,貧民を励まし,家なき人には住居を無償で貸与したり,救済宗教の導きを日に談じ,「死者を葬るだけが仏教ではない。この世に生きる人々に,希望とよろこびを与えることこそ,真の仏の道なのだ」という,まさに仏法の信念に徹した名僧であったと記されております。気仙三十三観音の御詠歌の作者ともあります。
英俊方丈様の慈善に心を打たれ,林野を寄進する人も多く,当時,金剛寺の持領がかえって増えたというのですから,名僧に応える良民あり,すばらしい郷土先人の偉業が偲ばれるものです。その人脈の広さや深さも加え,ご本人のお人柄によって各種の事業立案が実現できたと考えられます。合掌。
2016/09/02 11:00 |
2016年09月