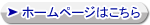子どもを「見る」
5月28日(金)
今日は、すこやかメールマガジンから【子どもを「見る」】という文章を紹介します。
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
さて、親同士の会話でよくあるのが「うちの子〇歳になったのに~~~ができなくて」「周りの子はできるのにうちの子はまだ~~~もできない」という内容ですが、私にも覚えがあります。もしかしたら、保育や学校教育の現場でもあるあるなのではないでしょうか。周りと同じようにできることの同調性による安心感を得るため、何歳頃には何ができているといった、いわゆる発達段階にあてはめて子どもを見ることが多いように思います。
しかし、発達段階から子どもをみることは、本当にその子のことを「みる」ことになっているのでしょうか。
玉川大学教授のマメ先生こと大豆生田 啓友(おおまめうだ ひろとも)先生は日本教育新聞の「個々の『いま、ここ』を受け止める」という記事の中で「発達の仕組みや道筋を理解しておくことは専門性として大切ですが、同時に子どもとかかわる上で発達の枠組み(できた・できない)で子どもを見ることの落とし穴に自覚的であることが必要だ」と述べています。
目の前にいる子どもは、毎日何かを発信し続けています。中には感情を爆発させたり、いわゆる発達段階にそぐわない行動をしたりすることもあるでしょう。
その発信されている多くの「何か」を単に発達段階に当てはめて評価し、指導するだけではなく、受け止めそして理解しようとすることも子どもを「見る」ということなのかなと感じました。時にはその発信を、大人も一緒に、周りも巻き込んで楽しめる、そういった雰囲気が、子ども達の成長に繋がるのだと思います。
みなさんは今日、子ども達の素敵な行動や場面を幾つ発見しましたか?
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
このメールは、「見る」ことの一つの視点を話しています。どこかの歌詞に、「No.1にならなくてもいい、もともと特別なOnly one」というのがありましたね。どの子どももそれぞれ違っていて、それが個性だと思っているのですが。親の目、先生の目、地域の目。それぞれ、見方がちがいますよね...。むずかしいですね...。
今日は、すこやかメールマガジンから【子どもを「見る」】という文章を紹介します。
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
さて、親同士の会話でよくあるのが「うちの子〇歳になったのに~~~ができなくて」「周りの子はできるのにうちの子はまだ~~~もできない」という内容ですが、私にも覚えがあります。もしかしたら、保育や学校教育の現場でもあるあるなのではないでしょうか。周りと同じようにできることの同調性による安心感を得るため、何歳頃には何ができているといった、いわゆる発達段階にあてはめて子どもを見ることが多いように思います。
しかし、発達段階から子どもをみることは、本当にその子のことを「みる」ことになっているのでしょうか。
玉川大学教授のマメ先生こと大豆生田 啓友(おおまめうだ ひろとも)先生は日本教育新聞の「個々の『いま、ここ』を受け止める」という記事の中で「発達の仕組みや道筋を理解しておくことは専門性として大切ですが、同時に子どもとかかわる上で発達の枠組み(できた・できない)で子どもを見ることの落とし穴に自覚的であることが必要だ」と述べています。
目の前にいる子どもは、毎日何かを発信し続けています。中には感情を爆発させたり、いわゆる発達段階にそぐわない行動をしたりすることもあるでしょう。
その発信されている多くの「何か」を単に発達段階に当てはめて評価し、指導するだけではなく、受け止めそして理解しようとすることも子どもを「見る」ということなのかなと感じました。時にはその発信を、大人も一緒に、周りも巻き込んで楽しめる、そういった雰囲気が、子ども達の成長に繋がるのだと思います。
みなさんは今日、子ども達の素敵な行動や場面を幾つ発見しましたか?
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
このメールは、「見る」ことの一つの視点を話しています。どこかの歌詞に、「No.1にならなくてもいい、もともと特別なOnly one」というのがありましたね。どの子どももそれぞれ違っていて、それが個性だと思っているのですが。親の目、先生の目、地域の目。それぞれ、見方がちがいますよね...。むずかしいですね...。
2021/05/27 17:00 |