2018年11月の記事
お見事!竹っ子の災害対応
 11月26日(火)第3回の避難訓練を行いました。3回目にふさわしく今回はちょっと難しい想定。
11月26日(火)第3回の避難訓練を行いました。3回目にふさわしく今回はちょっと難しい想定。日時予告なし!休み時間で学級ばらばら!教室にいるとは限らないから机の下に入れない!停電想定で放送中断!大地震の後に火災発生!
しかも、体育館の塗り替え工事中のためいつもの避難場所が使えない!校庭修復工事中のため、残された避難経路がガラス窓のそば!という例年にはない要素も加わりました。
その上、事前指導はしていたものの、実施予定日が雨で延期!教えられたことを忘れてしまいそう。
それなのに、いざ緊急地震速報が伝わると、その場に偶然に合わせた子どもたちが、さっとまとまって適切な場所を見つけて安全姿勢。ゆれが収まった頃、先生方の肉声の指示をしっかり聞いて、火元の反対に向かって避難開始。
中庭にいた子どもたちは、ガラス窓に近い経路を避け普段は入っていけない工事区内に入るという正しい選択をして、工事業者さんの誘導に従って避難。
整然と避難場所に向かうと、いつもとは違う場所に立つ安全旗。それでもその前に素早く学級ごとに整列し、全員の無事を確認しました。避難開始から確認完了までわずか3分弱!
竹っ子たちの臨機応変ぶり、的確な判断力にびっくりさせられました。通常では学ぶことができない特別な、でも災害時に実際に生きる学習ができたと思います。
校庭修復工事完成間近の実施でしたが、お忙しい中、工事を中断し訓練に協力して下さった照甲組の皆さんにも心より感謝申し上げます。
ハザードマップで災害への備え
 11月21日(水)全校児童が体育館に集まり、防災学習を開きました。
11月21日(水)全校児童が体育館に集まり、防災学習を開きました。震災以降、地震や津波に対する備えを重点に学習してきた子どもたちですが、山や斜面の多い竹駒町は土砂災害にも警戒が必要。さて、自分が生活している場所はどんな災害への備えが必要なのでしょう。それを調べることができるのが市のハザードマップです。
まずは、地域ごとにグループを作ってハザードマップの周りに集合。自分の家を表す付箋を貼って、家・通学路・一人でよくいく場所はどんな災害の警戒域なのかを調べました。そして、どんな備えが必要なのかを話し合い。どの子も真剣なまなざしでハザードマップを見つめ、わがこととして災害への備えを考えていました。
学習したことを記入したワークシートはおうちへ持ち帰り、防災について家族とも話し合うことにしました。
市長さんと語るふるさとの未来
いつもにも勝る澄んだ歌声。市の音楽発表会
 11月15日(木)市の音楽会で3~5年生が学校代表として合唱の発表をしました。歌ったのは「赤いやねの家」「語り合おう」の2曲。立派なリアスホール(大船渡市)のステージに緊張気味の子どもたちでしたが、そこは歌が大好きな竹っ子たち。いつもにも勝る澄んだ歌声を会場いっぱいに響かせることができました。
11月15日(木)市の音楽会で3~5年生が学校代表として合唱の発表をしました。歌ったのは「赤いやねの家」「語り合おう」の2曲。立派なリアスホール(大船渡市)のステージに緊張気味の子どもたちでしたが、そこは歌が大好きな竹っ子たち。いつもにも勝る澄んだ歌声を会場いっぱいに響かせることができました。子どもたちの振り返りを見てみると、自分の発表にも他校の発表にもずいぶん技術的なこと、態度的なことを細かく分析していました。細かいところまで丁寧に意識し、それを1つに合わせて歌うことができたから、あんなに素晴らしい発表ができたんですね。子どもたちに脱帽です。

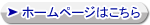

 11月21日(水)「市長と語る会」が行われ、本校6年生が出席しました。
11月21日(水)「市長と語る会」が行われ、本校6年生が出席しました。