学校行事
今年も「語り継ぐ会」。1回目講師は校長先生
 平成29年より始めた「震災を語り継ぐ会」。4年目の今年も全4回の予定で行います。
平成29年より始めた「震災を語り継ぐ会」。4年目の今年も全4回の予定で行います。毎年の1回目は、学習のオリエンテーションも兼ねて、校長先生を講師としています。
今年度の1回目は8月25日(火)。ソーシャルディスタンスをとれるよう、体育館で行いました。
校長先生は、今回特に、震災の時に勤務されていた学校が避難所となり、そこでの生活から学んだことを語ってくださいました。
生きるためにはまず飲み水とトイレが必要であること、がれきに埋もれた食料を沢水で洗って食べたり、体育館の暗幕を切って毛布代わりにしたり、知恵を絞って生きる努力をしたこと、平静を取り戻すためには非常時であろうと規則正しい生活をすることが大切であること、いつも通り暮らすことが実は尊いものであること・・・。
現在のコロナ禍の中での生活にも通じる大切なことを学びました。
竹駒小では、9月17日(木)に県の防災アドバイザーの方を講師に、避難所での暮らし方について防災学習を行う予定です。
防犯協会の皆さんと登校時避難訓練
合い言葉は「浮いて待て」
 7月17日(金)水難学会の指導員の方々4名をお招きし、着衣泳の学習をしました。
7月17日(金)水難学会の指導員の方々4名をお招きし、着衣泳の学習をしました。例年はプール納めの頃、9月に行っている学習ですが、実際の活用を考えると、水遊びの季節の前に行った方が良いと、今年度から時期を繰り上げての実施。対象も昨年度から全校児童としました。
写真は、1・2年生の学習風景です。ペットボトルなどの浮いている物を使えば、ちゃんと1・2年生でも浮いて待つことができるんですね。
併せて、水に落ちてしまった人の助け方も学びました。小学生は自分が水に入って助けることはせず、まず浮く物を投げてあげること、動いて体力を消耗しないよう「浮いて待て」と何度も言ってあげること、大人に知らせることが大切だそうです。
万が一が起こったときのために、命を守る方法を専門的に学ぶことができました。

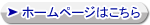

 2学期3日目、8月20日(木)に登校時避難訓練を行いました。
2学期3日目、8月20日(木)に登校時避難訓練を行いました。 7月14日(火)の児童朝会は保健委員会が夏の健康な生活について教えてくれる割り当てでした。
7月14日(火)の児童朝会は保健委員会が夏の健康な生活について教えてくれる割り当てでした。